
☎ 048-571-8355
FAX 048-571-1606


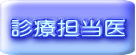


特色・診療内容 よくある質問
外来のご案内 入院のご案内 病診連携
手術実績 内視鏡実績


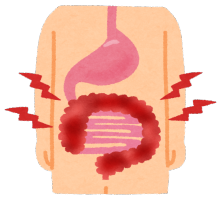 |
肛門からの出血(下血)で、大腸内視鏡検査を受けたら、「潰瘍性大腸炎」の疑いが強いと言われました。 「なにそれ?」とおもう方は沢山いると思います。ここで、その発見の経緯などを、当院のスタイルで分かりやすく説明したいと思います。 「潰瘍性大腸炎」は英語で「Ulcerative colitis」といい、通常「UC」と略されます。我々医療人にとっては、決して珍しい病気ではありません。2016年度の統計では、日本に約21万人いると言われております。医学生の時から勉強する病気なので、消化器を専門としていない医師でも名前は知っている疾患です。 ですから、この疾患を専門にしている医療機関のHPなどでは、より詳しく解説されています。まず「概要」をここで知って頂き、更に詳しい治療の内容まで求める方は、専門としている医療機関のHPなどを更にご覧になる事をお勧めします。 さて、当院では年間に約1,500件の大腸内視鏡検査を行っており、そのキッカケは様々ですが、10代から90代の方まで、老若男女の検査を行っております。その中でUCと診断される方は約40名ほどおります。「手術が必要な大腸がん」と診断される方が約50名いるのですが、その数よりは若干少ないという結果になっています。 また、年齢層も「大腸がん」よりは若い年齢層に発生し、20代でも発見されることは珍しくなく、むしろ、60~70代の方に発見される方が珍しいという病気です。全体の年齢分布からみると、20~40歳代に多く、大腸がんよりも若い層で発見されており、これは全国的な統計にも一致しています。また、原因は明らかなものはなく、「不明」とされております。稀に親がUCだったという方の子供に同様の病気が発見されることもあります。 どういった経緯から発見されるのですか? やはり、一番多いのは、肛門からの出血(下血)です。もともと当院はご存知の通り肛門科ですので、下血を主訴に大腸内視鏡検査を受ける方が多くを占めています。単純に、がんは若い人には少ないのですが、その出血をどこまで気にするかは本人次第になります。 当院の場合、「若いから、がんの確率は低いので、大腸内視鏡検査をは必要ないですよ」とは絶対に言いません。本人が「この前あった出血がとても心配だ」というのなら、中学生以上であれば、大腸内視鏡検査は躊躇しません。ちなみに、当院で検査をしている私(副院長)が経験した最年少の大腸内視鏡検査は14歳です。 しかし、外来に初めて来院し、その主訴(患者様が最初に訴える症状)が下血で、まだ30歳未満であれば、その時点で大腸内視鏡検査を積極的に勧めることは殆どありません。その理由は、下血の原因で一番多いのは、やはり肛門の病気である可能性が高いからです。殆どの場合は、裂肛(切れ痔)、痔核(いぼ痔)などがその原因であるからです。 まずは、一番出血の可能性が高い肛門周囲の病気が原因と思われるので、「坐薬や軟膏を処方して、2週間程度は薬を使ってどうなるか経過を見ましょう」という事を提案します。もしその期間で、気になる症状が消失すれば、「痔の薬」で治ったのだから、結果的に肛門周囲のトラブル、いわゆる「痔」が原因だったのでしょう、という事になります。 しかし、その出血が薬で治ったとしても、中には「やはりあの時の出血が気になる」と考える患者様もおますので、そういったケースでは、たとえ若くても大腸内視鏡検査を行い、出血の原因が大腸にあるのか無いかを調べます。 もしその出血の原因が「痔」ではなかったら、当然ですが「痔の薬」で治る訳がありません。結果的に大腸内視鏡検査を受けて、UCが診断された方の殆どは、「その後出血はどうなった?」の問いに、「あまり改善されませんでした」という方が多くいます。もちろん、のちに大腸がんと診断された方も、痔の薬で症状が改善する事はありません。 炎症の範囲・強さとは? 教科書的にUCは、肛門から入ったすぐの「直腸」から発生し、徐々に上(口側)に粘膜面(表層)に炎症を広げて、S状、下行、横行、上行結腸、盲腸(詳しい解剖はこちらへ)へと、炎症が広がっていくと言われています。という事は、検査をする側からすると、UCの発見の多くは、内視鏡を入れたその瞬間に分かる事が多いという事になります。 特に当院では外来の診察の時点で肛門鏡を用いて診断しておりますので、実はこの初診の時点で、その疑いがあると察知する事ができてるのですが、それを確定的にするために、後日大腸内視鏡検査をを勧めております。 正常な大腸粘膜は、ピンク・オレンジ色の粘膜面に血管が網目状に透けて見えます(画像はここでは出せませんので、「大腸粘膜 正常」で検索して下さい)。ですが、UCの粘膜は血管が透けて見えず、むくんで厚ぼったく、粘液の産生が過剰な結果「白い斑点」がみられ、軽い摩擦程度で出血し、「赤い斑点、褐色の斑点」などが多数存在します。 内視鏡を肛門から挿入すると、その「好発部位」である直腸が一番最初に観察されるのですから、いきなりそのような「光景」に出会うのです。そのような状態が観察された瞬間、我々は次に何を考えるかというと、「この異常粘膜がどこまで続くのか」という事に瞬間的に切り替わっています。 15cm程度で炎症を起こしている粘膜が終わっていれば、最も炎症の範囲の狭い「直腸炎型」、大腸の半分くらいまでが侵されていれば、左半分の大腸が炎症を起こしているので「左側大腸炎型」、そして炎症が大腸の最も奥とされる盲腸にまで及んでいれば「全大腸炎型」と分類されています。 また、その特徴的な粘膜像でも、なんとなくUCらしい粘膜をしているのかな?という程度の軽い炎症から、色調の変化が強く、粘液などが多量に産生され、白い粘液が激しく付着し、少しカメラが擦れた程度で、ジワジワと出血してしまうような、非常に炎症の強いもまで、「炎症の強さの程度」というものがあります。 どちらも、炎症の範囲にしては直腸だけで炎症が留まっている「範囲の狭い症例」が、炎症の強さは、「程度の軽い症例」の方が多く発見される傾向にあります。 「教科書的」という言葉はあくまでも典型例であって、医師国家試験レベルでは、「直腸から連続する病変」という事ですが、臨床の現場では、直腸は正常であっても、S状結腸に炎症があり、そのすぐ奥は正常粘膜に戻っても、最も奥の盲腸でまた炎症があるというような、連続していない症例も時に存在します。 これを読んでいる医学生は、そこまで病気の可能性を追求する必要はあまりないと思います(最近の国家試験の内容までは把握していませんので、細かいコメントはできませんが)。 下血以外の特徴的な症状は? やはり腸自体に炎症が起きていますので、「下痢・軟便傾向になった」という方が多くいます。そして、時に「粘液みたいな、白~透明な液体が出る」といった症状が数ヶ月前からありました、と訴える方が多いです。また、腹痛や、発熱、そして、症状が強くなると、体重減少などが見られる場合もあります。 もしこのような症状が出ても、すぐに医療機関を受診する方は多くありません。それが、さすがに数ヶ月も継続するとなると、「今までこのような事は経験した事が無い」と心配になり、検査を受ける事が多いので、発症から発見までに数ヶ月かかるケースが多いというのは、このような理由からです。 そして、上で述べた炎症の範囲が広ければ広いほど、炎症の程度が強ければ強いほど、症状も強くなるのが一般的です。そして、下血の量が多ければ当然「貧血」の症状が強くなります。大した運動もしていないのに、すぐに息が上がってしまったり、めまいがしたり、立ち眩みが強くなったり、「顔色が悪くない?」と言われたりします。 |
||
| 診断・治療は? 診断は、大腸内視鏡検査をしないことは始まりません。特徴的な粘膜が確認できたら、「生検」といって、粘膜の一部をいくつか採取します。粘膜面に痛みを感じる神経はありませんので、痛みは伴いません。そして約一週間後に顕微鏡で観察した結果が届きます。多くの場合、「これはUCです!」というような確定的な結果ではなく、「特徴的な構造物が見られますので、UCが強く疑われます」といったようなニュアンスの結果が届きます。 この時点でほぼ診断は確定します。さて、診断されたら、次は治療の段階に移ります。 例えば「風邪」で考えてみましょう。誰もが経験した事はあると思いますが、「風邪ひいた → 風邪薬を飲む → 風邪が治った → 飲むのをやめる」、となります。では、「高血圧症」はどうでしょうか?「血圧が上がった → 降圧剤を飲んだ → 血圧が下がった → 内服をやめる」、とはなりませんよね?薬を飲むのをやめたら、きっとまた血圧は上がるでしょう。 この2種類の病気の大きな違いは、「治す病気なのか」、「抑える病気なのか」という点です。更に言えば、薬は、「治ったらやめられる」、「治っても継続しなければならない」、というのが一番大きな違いです。UCはその病気の性質上、高血圧症の様に、「抑える病気」なので、継続的な薬の使用が必要となります。 症状の強さ、炎症の強さ、範囲などから、治療の種類は多岐に及びますが、それをここで全て述べていてば、とても語り切れないので、最も沢山の方が見つかる、軽症の治療について述べさせて頂きます。 軽症の中でも程度がありますが、「飲み薬単独」か、「坐薬単独」か、あるいは両方が必要になります。ファーストチョイスの薬の多くは「5-ASA製剤(ごあさせいざい)」と言われております。最短でも薬の投与必要期間は約2年と言われています。外来受診から大腸内視鏡検査の日まで痔の薬を使っていた期間に症状の改善が見られなかったのとはうって変わって、UCの治療薬を使用し始めると、次第に症状が改善してくる方は割といらっしゃいます。 ですが、症状が完全に消えても、すぐに薬をやめる事ができないのがこの病気の特徴で、まずは1年経過したら、症状が消失していても、炎症をおこしていた場所を一度観察をする事をお勧めしています。すると、自覚症状が消えている方は大抵、特徴的な粘膜も消失して、正常の大腸粘膜に置き換わっているか、かなり改善されている粘膜を確認する事ができます。このような状態の事を「寛解(かんかい)」と言います。 治療の目標は、症状が消失するまでではなく、炎症を起こしていた粘膜が正常化(粘膜治癒)している事を内視鏡で確認できるまでです。また、治療開始後2年が経過した時点で、薬をしっかりと継続していれば、「寛解」の方が9割いるのに対し、症状が一時的に消えたので、薬を使わなくなってしまったり、自己判断で止めてしまったりすると、寛解は4割に留まるという結果も出ております。 最初は、「そんな長期間飲むの?」と思いますが、患者さん自身も様々なHPでこの病気の事を調べて、一年後の時点で病気が消失していても、その時点で継続してきた薬を中断する勇気というものがなくなり、逆に継続していないと不安、という気持ちが強くなっている方もいます。そして、2年後を迎えた時、それまで飲んでいた薬の量を減らして様子をみる、という方が一番多いパターンです。 その後、どの時点で薬をやめるかというのは、症状の出方などをみて、慎重に担当医と決める事になります。 しかし、このような薬だけで顕著に症状が改善されないケースも少なからず存在します。その先の治療はステロイドが必要となったり、さらなる治療が必要になる事もあります。このような、初期投与の薬で抑えきれないUCに対しては、専門としている消化器内科の先生に紹介する事になります。その先の詳しい治療法は、他のHPで情報を入手して頂くか、専門としている先生に話を伺って下さい。 当院では、現在100名程度の薬でうまくコントロールできているUCの患者さんを経過観察しております。 治療しなかったらどうなるのか? まず、血便の頻度が多くなる事から、貧血などの症状が強くなる、というのが容易に想像できると思います。また、上にも述べましたが、腹痛や、頻便の程度が増強したり、発熱が持続する事もあります。しかしこれらの症状は「短・中期的」なものです。もし、炎症を何年も治療せずに放置してしまうと、体重が異常に減少してきたり、稀に大腸がんが発生する事があります。つまり、大腸がんのリスクが高まる事になります。 しかし、しっかりと炎症を抑えておけば、UCの無い人とほぼ同等の大腸がんリスクに減らす事が可能であると言われております。ですから、軽症のうちに発見して、しっかりと治療をしておく必要があるのです。 しかし、中にはどんな治療を施しても炎症が抑えられない方もいます。私自身もこれまで20年以上消化器の診療をしてきましたが、数名程度ではありますが、そのような激しい炎症を抑えきれないUCは、外科的に大腸を切除するしかありません。しかし、ここまでいくのは、UCの患者さんの中でもかなり稀だと思って下さい。 この病気で最も大切なのは、しっかりと薬で炎症を抑えておく事です。 |